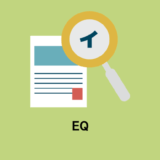アクティブラーニングとは『能動学習』
 新人
新人
 先輩
先輩
『アクティブラーニング』は、最近ちょくちょく話題にのぼる言葉です。『能動学習』の意味で、教育について関心のある人にとっては重要なキーワードのようですが、一般的にはまだまだその意味が浸透していませんよね。
ここでは、アクティブラーニングの持つ意味を、それが生まれた背景も含めて解説するので、しっかり覚えていってください。
アクティブラーニングの意味をチェック
アクティブラーニングとは、『能動的に学ぶことを奨励する』という意味の、教育界で大変注目されている学習方法のことです。
アクティブラーニングは幼稚園から小中学校、高校、大学まで、多くの教育機関ですでに取り入れられています。なぜなら、国の教育方針を決める文部科学省が、積極的にアクティブラーニングを推奨しているからです。
文部科学省の新指導要領においても、アクティブラーニングを用いた授業の改善や推進について言及されています。
アクティブラーニングが生まれた背景
アクティブラーニングが生まれた背景としては、近年の急速なグローバル化や少子高齢化という環境の変化が挙げられます。
かつての日本の製造業を軸としたモノづくりの先進国としての姿は、前述の環境の変化により失われつつあります。
発展途上国との競争にさらされる日本では、詰め込み型教育では技術革新につながらないという危機感が生じはじめました。
そういった背景のもと、大学教育を皮切りに教育の各段階においてもアクティブラーニングを大いに推進しようということになったのです。
アクティブラーニング実施におけるポイント
アクティブラーニング導入の初期において、多くの先生は、本当に子どもたち主体で授業を進めていけるのか気がかりだったようです。しかしほとんどの場合、それは大人の勝手な思い込みで限界を設けていたと省みることになったようです。
つまり、先生サイドの思い込みで不安を持って行うのではなく、子どもたちの力をもっと信じて確信的に行うことが大切となります。
そしてもうひとつ大事なことは、授業を進めるにあたって、先生が「適切に声掛けすること」です。迷っている様子や何か相談したい様子などを敏感にキャッチして、先生の方から声を掛けてあげるのです。それによって、子どもたちのやる気や意見を引き出すことができます。
 上司
上司
アクティブラーニングの英語は『Active learning』
アクティブラーニングは英語で『Active learning』と表記します。使い方は日本語の場合とまったく同じです。
以下のように使われます。
千葉のある私塾が小学生向けの体験学習プログラムを開始しました。
アクティブラーニングとケーススタディの違い
アクティブラーニングとケーススタディは、密接な関係にあります。違いというよりは、ケーススタディはアクティブラーニングの範疇に入るひとつのメソッドともいえます。
ケーススタディは実際に起きた事例などを題材に使い、どうすれば最善の解決策がとれるのかを話し合ったり考えたりする学習法です。
ケーススタディは欧米ではかなり普及しており、外資系の企業の面接試験にも用いられます。問題を解決する力やリーダーシップの素養を見るためでしょう。
アクティブラーニングの使い方・例文
あまり日常では使わないアクティブラーニングという言葉ですが、ビジネスシーンにおいてはどんな使われ方をするのか、例文で見てみましょう。
 上司
上司
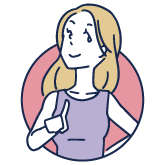 先輩
先輩
 新人
新人
[おまけ]ディープ・アクティブラーニングの提唱とは?
アクティブラーニングが学習の形態にフォーカスしているのに対し、ディープ・アクティブラーニングとは学習の質や内容の深さにフォーカスした学習法です。
文部科学省は京都大学の教授が提唱する、このディープ・アクティブラーニングを参考に、以下のような課題を挙げています。
アクティブラーニングにおいて、議論やプレゼンなどを多用した授業フォーマットに注目が集まりすぎて、逆に学生が受動的になってしまっている矛盾です。大学でのそれはアクティブであると同時に、ディープでもあるべきだというのが教授の主張であり、教育現場での実践につなげるための書籍も書かれています。
従来の学習との意味の違いを理解して使おう
アクティブラーニングはいまだ課題があり、完璧な学習法ではないかもしれません。それでも従来のものとは一線を画すアプローチであるのは確実です。『アクティブラーニング』という言葉を使うときは、従来の学習アプローチとの違いをしっかり理解して使いましょう。