ビジネスパーソンのための「秘書力」養成講座の要約を紹介


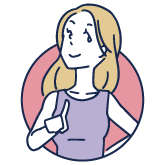
ビジネスパーソンのための「秘書力」養成講座は、タイトルの通り、秘書が実践している仕事のノウハウを学べる本です。ちょっとした気遣いや効率アップの方法を学べるので、ビジネスパーソンに広くおすすめできます。
もともと気が利いたり、気がついたりすることに長けている人だけが秘書力を発揮できるのではなく、こうした本から「学ぶ力」がある人も自身の強みにしていけます。
普段はごく一般的な中間管理職をしている私も、真似したい仕事術がたくさん詰まっていました。一度習得すれば長く使えるスキルとなるので、この本でぜひ秘書力を高めてみましょう!
ビジネスパーソンのための「秘書力」養成講座の目次
第1章 秘書力とは、「段取り力」
第2章 秘書力とは、「確実力」
第3章 秘書力とは、「気づき力」
第4章 秘書力とは、「問題解決力」
第2部 関係構築編
第5章 秘書力とは、「接遇力」
第6章 秘書力とは、「コミュニケーション力」
第7章 秘書力とは、「信用力」
第3部 自己成長編
第8章 秘書力とは、「学び力」
第9章 秘書力とは、「成長力」
本書は上記のように大きく3つのパートで構成されています。まず始めに実際の業務遂行における気配り、段取りなどが解説され、次に関係構築のコツについて書かれています。そして、最後に自身の学びや成長に関する説明があります。
この本に書かれていることは理解して終わりではなく、実践に移すことに意味があると感じます。一度読んだだけで全てアクションに移すのは難しいので、まずは概要をつかみ、明日から実践できそうなものを一つずつ順番に取り入れてみるのがおすすめです。

第1部「業務遂行編」で学べること
最初のパートを読んでみてわかったのは、「相手の立場になること」や「確実に仕事を進めるフロー」が非常に大切だということ。この2点について概要をご紹介します。
相手の立場で考える
秘書は、自分と上司の予定を管理しなければなりません。上司が出張に行っていたら、「新幹線に乗って1時間経ったから寝ているだろうか?」など相手の立場で考えるのが大事なのだそう。おまけの資料をつけるかどうか迷ったら、普段の上司の発言や様子から、何を求めているのか考えて対応します。
ただ、ありがた迷惑になることもあるので、なんでもかんでもすればいいわけではありません。完璧で丁寧な資料を求めるのか、体裁よりも正確さとスピードを求めるのかなど、上司によって期待するものに違いがあります。相手にとって何が必要で、何が不要なのか、日頃から頭にインプットしておくことが大切になります。
ミスなく確実に
ミスや漏れがないように仕事を進めるのは、単に「意識する」という自身の努力ではなく、仕組みが大切となります。例えば、メールの返信忘れをなくすために、対応を終えたメールは別フォルダに入れる。添付ファイルは先につけてしまう。こうした具体的なノウハウが紹介されています。上司の出張で手配モレを防ぐフローなど、真似したいものが多くありました。

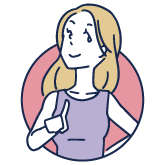
第2部「関係構築編」で学べること
関係構築編では、主に接遇力について解説があります。秘書にとっては欠かせないものですが、どんな仕事にも多かれ少なかれ接遇力は必要となるため、ぜひ参考にしたいところです。
■挨拶:しているかではなく、相手に届いているか。
■身だしなみ:判断するのは相手。お客様、上司の服装、場所、仕事内容から考える。
例えば、高級腕時計でステータスをアピールでき、トークが盛り上がるケースもあります。一方で、お客様の支払ったお金で給料が出ており、そこから買った高級時計だと思われてしまうこともあります。そんな例を引き合いに出し、持ち物を客観視することの必要性を説いています。

第3部「自己成長編」で学べること
自己成長編では、学ぶための考え方について解説されています。本書の著者は気配りのセンスや才能があるように思えるのですが、やはりご自身でも学ぶ努力をされてきています。
それがわかるエピソードが、上司が対応中に上司あての電話が入り、電話があった旨をメモに書いてお見せするときの話です。メモに「中座して電話に出る」「折り返すと伝える」と2つの選択肢を書いて上司に見せ、言葉を発さなくても指示ができるように配慮したというもの。
これは、著者がオリジナルで考えたのではなく、本で学んだことを実践したのだそう。書籍や人を参考に、向上心を持って吸収、実践していける人になりたいものです。
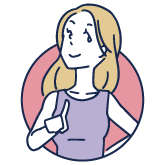
ビジネスシーンで気配り力と効率をアップ
ビジネスパーソンのための「秘書力」養成講座では、仕事上で相手に喜ばれる気配り、そして仕事の効率自体をアップさせるヒントがたくさん詰まっています。仕事をするすべての人におすすめしたいと思える本でした。ここに書かれていることが実践できる人材は、重宝されること間違いないでしょう!


